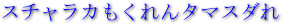
※ボタンの上にマウスを置くと説明が出ます
空を覆うは羊雲。木々を彩るは種種様々な色彩の紅葉。 虫たちは冬を過ごすための食料の採取にせっせと働き、 人間様はお気楽にも食欲の秋、読書の秋、運動の秋と楽観を決め込む、そんな季節。 絵の具で作ることの出来る色の数を遙かに超えた色調は、 無残にも地へと重力に引かれて、果ては人に踏まれて極彩色は滲む。 だが、死骸はやがて地へと還り、再び木々の緑を彩り出す。 つまり、今季節は秋真っ盛りなのであった。 ここに、秋の景色に囲まれた街道を進む旅人の一行。 ちょいと珍しい事に女の二人連れであった。ただ、ここ大陸北部は そこそこ治安は安定しているので、要らぬ心配は無用かもしれない。 街道の左を歩く女は辺りの景色にさしたる感慨を受けた風もない。 適当に後ろで括られただけのざんばら髪なのだが、不思議と野蛮さよりは 力強さを見る者に感じさせる、そんな女性である。 その顔は十分に整っていた。だが彼女の美貌は自身が発する一種独特の気迫にあった。 その隣を歩く幾分幼めの少女は辺りの景色に眼を輝かせ見入っている。 飾りっ気の無い服装のなかで、涙の形をした耳飾りが光り輝いていた。 年頃の少女の心を表すかのように。 二人連れの旅といえば、余程仲が良くなければするもんじゃあない。 喧嘩のときは仲裁相手がいないし、長い旅の中では気まずい思いが芽生える事も それなりにあることだ。 ところが、この二人はというと、それこそ親の敵か恨み骨髄の敵将かを 目の前にしているかの如くに視線を争わせていた。 ギスギスとした雰囲気は周りに伝播し、近くの通行人は皆、この二人を避けてゆく。 しかし、二人はその事には全く気付いていないようである。 激しく相手を睨み付けながらも、急ぎの用事があるかのように すたすた、すたすたと早足に進んでゆく。すたすた、すたすたすた。 「あの〜お二人とも。周りの迷惑になっている事に気が付きませんか?」 どこからともなく聞こえてきた声。それは二人にだけ聞こえる声。 「それなら梨乱の所為だな。あいつに注意しといてくれ」 ざんばら髪の女が答える。 「それなら夜主さんの所為よ。本当にいい歳して、もう」 頭に鉢巻をした少女が答える。 二人の諍いを仲裁しようとした声の主は、夜主と呼ばれた女の指に填められている 指輪である。驚くのも無理はない、普通指輪は喋ったりはしないものだ。 だがこの指輪はそんじょそこらの指輪じゃない。とある事情で地上にばらまかれた 七二六個の欠陥宝貝が一。名は『捜魂環』。 二人は夜主を縛り付けている手錠の宝貝『動禁錠』の呪縛を断ち切る為に 和穂という娘を目指して旅を続けている。その長い旅の中、それこそ毎日の様に、 二人の間では喧嘩は絶えたことが無かった。喧嘩するほど仲がよいとは言うけれど、 これもそれに含めるものかどうかは議論の余地があろう。 勿論、そんなことで順調に旅が続くはずもないのだが、 目標とする和穂までの距離は少しずつとはいえ近づいていた。 まあ、その辺の事情はまた今度にでも。 街道はいつしか小高い丘へさしかかっていた。 坂道を越えれば、今日の宿を取る予定の町が見えるはずだ。 「もうそろそろ町が見える頃ではないかい、梨乱ちゃんよ」 「そうね・・・。今夜はふんわりした布団の上で眠れそうね。 ここんとこ野宿だったから体のあちこちが痛くて痛くて」 「はっはっはっ。笑わせてくれるじゃないか梨乱ちゃんよ。 そのちっぽけな採譜の中身でどうやったら、ふかふかもこもこの布団で 眠れるというのだい? それに・・・さっきの発言はおばさんくさいぞ」 「・・・う、確かにそうかも。 でもまあ、夜主さんだって野宿したいわけじゃないでしょ?」 当然、夜主も梨乱の意見と同じ見解を持っていた。 たわいのない口喧嘩を応酬しつつ、二人は一歩一歩堅実に 坂道を踏みしめ登ってゆく。もうすぐ上り坂も終わりだと気を抜いてはいけない。 坂道を下りるときは、登る時と同じかそれ以上の注意を要するのだから。 ゆっくりとした足取りで丘のてっぺんにたどり着いた彼女たちが目にしたものは、 頑丈そうな高い岩壁に守られた町の姿であった。 「・・・なあ、これは私の目の錯覚か? それとも近頃では城壁で町を囲むのが 流行っているのか?」 「そんな流行なんて知らないわよ。でも、よっぽどの事が無ければ、この北部で あんなに防備を固める必要なんてないはずなのに」 梨乱達が旅している大陸北部は、小国が乱立していて、常に相手の領土を併合せんと 各国が虎視眈々と機会を狙っているような南部とは全く違う。 ここが南部なら、どこかの独立している地方都市と考えただろうが、 如何せんここは北部なのである。 その事を考え合わせると、この村は不自然と言う他に無い。 不自然を通り越して奇異と言った方が良かろうが。 他の旅人達も流石にこんな有様は予想していなかったらしく、 普通想像するのは稲のたわわに実った田圃とかであるが、 一様に驚き、立ちつくしていた。 「悩んでいても始まらないわ。さっさと進みましょう。 幾ら何でも城門を警備していたりはしないでしょ」 これは梨乱にとっては冗談のつもりだったのだが、 周りの人々は警備員に取り押さえられたらどうしよう、 等と杞憂する者まで現れる始末だった。 だが、例え杖を持った警備員に行く手を阻まれても、袖の下を要求されたとしても、 梨乱達にはその村に立ち寄らないと食料や水が尽きて困ってしまう、 という事情があった。まだ双方ともある程度は残っていたが、これからの事を考えると 是非ともこの村で補給しておきたいのだ。 村に近づくにつれて、村への違和感、二人の不信感は募る一方であった。 「梨乱よ、これは村どころか一個の都市ではないか。 この岩壁の強度、高さ、そして鉄の扉に壁の上に取り付けられた 連弩系の強弓といい、どんな相手を想定して作ったんだろうな」 梨乱は考え事をしていたため、答えなかった。 「どうした。何か気になる事でもあるのか?」 梨乱が口を開く。が、その表情には暗い影が落ちているようにも見えた。 ただ、腐れ縁も長くなってきた夜主には、その瞳の奥に輝く期待と神秘を 見つける事は容易かった。 「ほう、楽しそうな眼をしてるじゃないか。私にも話してみな」 「夜主さん。この岩壁をどうやって造ったと思う? もうこれは城壁と言っても差し支えないわ。 それを、村の人口で造ったのよ。どれだけの労力と時間がかかるでしょうね。 でも、皆さんの驚きようから言って、短期に造られた事は間違いないわ。 さて、これらの謎を繋ぎ合わせて一枚の絵とする鍵とは?」 「・・・言われてみればそれもそうだな。 もしかして、これも宝貝の仕業だと言いたいのか? しかも、宝貝を持っていながらここまでの防備が必要な相手がいる。 ということはそいつも宝貝使いなんだろう?」 「そう。私もそう思うわ。興味深いよね。これほどの壁を必要とする 敵とは一体どんな相手なのか。そして、その宝貝の能力とは」 一人で盛り上がる梨乱を冷たく眺める夜主。 「どんな宝貝だろうと、私の趣味には合いそうにないな」 それまで光射していた広野から、突然光が消えた。 のんびりとした口調で夜主は呟く。 「おや、夕立かな。季節も季節だからな」 梨乱は空模様を見ようと頭上を見上げた。それっきり硬直する。 「・・・や、夜主さん。ねえ、あれ」 あくまで夜主はのんびりと言葉を紡いだ。 「一体何だってんだその面は。今日はいつにも増して奇妙な面だな」 気に障る夜主の台詞は顔を引きつらせる事だけで何とか耐えて、 梨乱はただ自分の頭上を指差した。 指の向いた方向を仰ぎ見て、今度は夜主がたっぷり時間をかけて動きを止める。 二人が見たモノは、人の顔。ただし、通常の十倍はあろうかという、巨大なそれ。 「に、逃げるぞ梨乱。あんな奴とはお近づきになりたくないからな!」 近づいたら踏まれてお終いだと思うが。 夜主の履く靴もこれまた宝貝だった。人に風の速さを与える宝貝『俊地踏』。 梨乱の襟首をひっ掴み、夜主は城壁目指して走りだす。 「だ、だから、こういった運び方はしないで欲しいんだけぢょっ」 梨乱は抗議したが、大地を疾駆する振動に翻弄され、舌を噛んでしまい それ以上文句を付ける事は断念した。 俊地踏の欠陥は移動時の衝撃から使用者を保護する機能がない事である。 夜主はホンの七歩ほど走ったかと思うと ぴたっ、と急制止をかけた。 だが、空中に浮く格好となっていた梨乱は止まれない。 物理法則に従って、梨乱は夜主の手を離れて宙へと舞った。 ぶわほっ! クルクルと三回転半ほど回転してから、何やら豪快な音を立て、 梨乱は頭から地にめり込んだ。 そんな梨乱には目もくれず、夜主は眼前の巨人を見つめた。土色をしたそれを。 動くたびに体が崩れ、砂となって積もっている。 「フン。驚かせやがって。砂人形のくせに、この夜主をなめるんじゃないよ」 俊地踏の力を借り、風と同化して夜主は巨人の足を狙い、拳を突き出す。 ゴキッ。 骨の砕ける嫌な音が辺りに響いた。その音は夜主の右手から発せられた。 見た目脆そうな土の固まりは、その実、鉄の強度を誇っていたのだ。 夜主の攻撃など蚊に刺された程にも感じていないのであろう、 巨人は変わらず歩みを進める。その先には、未だに地面に埋まっている梨乱がいた。 砕けた右手の事はひとまず忘れ、無事な左手で己の全体重を支え、 しなやかな動きで足を振り回す。鉄よりも固い宝貝の靴で覆われた足は、 夜主の目論見通り巨人の足を潰してくれた。 足を失い、もともと平衡の悪かった巨人は大地へと倒れ込んだ。 大事をとって利き手を使わないでいたことは正解だったようだ。 梨乱が巨人の下敷きにならないよう計算された打撃は、 目論見通り梨乱に覆い被さらない位置に巨人を転倒させた。 さてと後は梨乱を掘り起こすか、と注意が逸れた瞬時が過ぎた後には、 巨人は元通り大地を睥睨して立っていた。そして潰される前と同じように進み始めた。 いつの間に足を修復した!? だがよく見てみると、体が幾分か 足を潰す前よりも小さくなっていた。胴体の土を使って足を造ったのだろう。 それならば完全に無くなるまで足を潰すまでだ、と再び足に狙いを絞った夜主に、 見知らぬ男の声が聞こえてきた。まだ若そうな、張りのある若者の声である。 「どけぇ、邪魔だお主。そこにいてはわしが巨人を倒せぬ!」 面白い。倒せるものなら倒して貰おうじゃないか、と身を引いた夜主の横を一陣の 颶風が薙ぎ払ってゆく。鋭く研ぎ澄まされた烈風は巨人を切り払う。 だが、これで倒せるのならば、夜主のさっきの一撃で既に巨人は事切れているはずだ。 * 「お前、何者だ?」 崩れ落ち、風にさらわれて微かにその名残を留めた巨人の前で、 梨乱を掘り起こした夜主が自分たちを救った若者に放った第一声がそれだった。 「無礼な奴だのう。少しは感謝してくれても良いだろうに」 若者は、青と白と黄、この三色のみで構成される衣服を纏っていた。 その背中は、昆虫の羽の様に二枚に別れ、頭には珍しい結び方の頭巾を被っていた。 年は二十歳足らずだろうとその顔から判断した。 もっとも、その衣服は見ようによっては…… 「やかましい家庭内害虫男。さっさと持っている宝貝を渡しな」 巨人を倒した颶風は宝貝が巻き起こしたものと、夜主は考えていた。 「渡してもよいがお主らではとうてい……いや、お主なら使えるかもな」 若者は言ってじっと夜主を見つめた。懐から一本の棒を取り出し、 だがそれを夜主ではなく、梨乱に渡した。 「使ってみるがよい。集中して「疾」と唱えながら振ればいい」 実に簡単な手順だった。だが、棒を握った梨乱は突然その棒を空中へ放り投げた。 夜主が問い質す間もなく、梨乱はがっくりと膝を落とす。 「な、何よこれ……!?」 荒い息を吐く梨乱。夜主の疑問に答えてくれる様な状態ではなさそうである。 カランカラン、と意外に軽い音を立てて転がる棒を夜主は掴んだ。 と、急激な疲労感が夜主を襲った。夜主の「仙人並み」の精神力が まるで湯飲み一杯分のお茶を飲み干すかの様に吸い取られてゆく。 その消耗する気力を無理矢理掻き集め、 「疾!」 そよ風が吹いた。それが夜主にとっての限界だった。 梨乱に続いて、夜主も身動きさえ満足に取れなくなり、二人揃って地面に寝ころぶ。 「ど……どうなっているのだこの宝貝は!?」 異様なのは何も急激に力を消耗する事だけではない。 今まで夜主が手に入れてきた宝貝には、曲がりなりにも意志というものがあり、 欠陥をそれとは無しに伝える位の仮想意識を持っていた。 だが、この宝貝からは一切の意志というものが感じられなかったのだ。 『……夜主様、夜主様……』 小さな声で、控えめに捜魂環が夜主に声をかけた。 『この宝貝からは、龍華の魂の反響が感じられません……』 『どういうことだ!?』 そう。和穂という娘が人間界にばらまいてしまった宝貝たちには、 制作者たる龍華の魂が微かに反映されているのだ。 それを音として感じ取ることによって捜魂環は捜索系の宝貝として、 人だけでなく宝貝も探す事が出来るのだ。 すなわち、この宝貝から龍華の魂が感じられないということは、 この宝貝は龍華の作ではない、ということになる。では一体この宝貝は? 『はい、これは私の想像ですが、これは古式宝貝ではないかと。 私たちとは比べ物にならない程強力な能力を持ち、 その反面、極めて使用者を限定する宝貝です』 「ふむ、その通り。確かに、これは古式宝貝だよ。 だが、古式宝貝を使える程の精神力を持った者と出会うのは実に久しぶりだのう」 夜主と捜魂環の心の中で繰り広げられていた会話に、若者が乱入してきた。 どうやら、今までの会話は全て聴かれていたらしい。 『心を読むことが出来るとは、あなたは仙人ですね?』 「必ずしも、心が読める事と仙人である事とが結びつくとは思わぬが……。 まあ一応、ワシは仙人だろう。とっくに破門されたも同然だが」 言って若者は苦笑した。 世に地仙という存在が語り継がれている。仙界で修行を積み仙人となって後、 人間界で暮らすことを選んだ者。世に出ることを潔しとせず、 隠者となって生きる彼らは、人間からは敬意を以て、 仙界に住む仙人たちからは軽視を以て、地仙と呼ばれていた。 * そろ〜りそろりと夜主は若者の背後へと回り、 獲物を狙う鷹の如き勢いをもって手を伸ばす。 だが、若者の持つ宝貝の生み出した風によって遠くへ弾き飛ばされてしまった。 「くそうっ、もう少しだったのに」 「いい加減に諦めなよ夜主さん。相手は仙人なんだからさ」 「そもそも、飛び道具は嫌いなのではありませんでしたか、夜主様?」 地仙の若者と出会って早三日。さっさと和穂と合流するべき二人だったが、 夜主が若者の持つ宝貝にいやに執心したため、防壁で囲まれた (この防壁も若者の持つ宝貝によって造られたそうだ)この町に滞在する事とした。 夜主の骨を砕かれた右手の治療も必要だったのだが。 この三日間、傷をおして幾度となく夜主は若者の宝貝を盗もうとしていたのだが、 その努力は尽く無に帰していた。少なくとも今までの所は。 ある日は落とし穴に落ち、ある日は偽物を掴まされ、 ある日は砂漠のど真ん中へ飛ばされたこともあった。 だが夜主はしつこく、いつになっても諦めない。 何度か例の土巨人も襲ってきたが、その度に若者によって撃退されていた。 梨乱もそろそろこの茶番に飽きてきた頃、若者は一つの賭を夜主に提案してきた。 それはこういうものであった。 「もし、お主が敵の宝貝使いを捕まえる事が出来れば、この宝貝はお主にやろう。 だが、ワシが先に見つけた時は、お主にはワシの宝貝は諦めてもらう」 夜主はその条件を呑んだ。そしてその夜、若者の姿は町から消えた。 そして翌日。 「探せ探せ梨乱! あのガキが見つけるより先に私達が宝貝使いを見つけだすんだ!」 じとっ、とした目で梨乱は言い返す。。梨乱はあの宝貝に対して夜主ほど熱心に はなれなかった。手に取るだけで気力体力ともに尽きてしまうのでは、 研究のしようもない。それでは如何にもつまらないではないか。 「そんな事言われても手がかりの一つもないんだけどね。向こうと違って」 若者が町から消えたというのならば、若者は宝貝使いの情報を握っているのだろう。 ということは、夜主の負けは、既にかなり色濃いものとなっているのかもしれない。 この時、梨乱には若者が逃げたという選択肢は考えに入れていなかった。 「で、出た。巨人だぁ!」 一刻も早く宝貝使いを探し出さなければならない、 そんなときに巨人は町を襲いにやってきた。 運の悪い時には悪いことが重なるものである。 「夜主さん、巨人を倒さないと」 「ええいやかましい、敵の宝貝使いを探し出せば万事丸く収まるじゃないか」 「そういうことは敵の位置が分かっている時に言って頂戴。 ともかく、巨人を先に叩くわよ」 「どうやってだ? いくら潰しても再生しやがるし、根こそぎ潰しても きっと明日には全く何もなかったように、 そりゃこの世で大地が尽きることは無いからそりゃそうなんだが、 ひょこっと表情の無いあの顔が出て来やがるに決まってる!」 「うっ・・・」 言葉を無くした梨乱が町の安否など二の次といった夜主を止められないでいると、 夜主の行く手に、町人たちが立ち塞がった。 「さっさとあの巨人を倒して下さい。お願いします!」 「何だと? 私があの化け物を倒さないといけない義理なぞ」 町人の一人が一枚の紙を夜主へと差し出した。若者からの手紙らしい。 『ワシのいない間に巨人が来襲してきた場合は、額に鉢巻をした職人風の娘と一緒の、 いかにも目つきの悪そうな、手を触れたら火傷じゃ済まないと思われる女に 対処を任せよ。なお、女がこの指示に従わなかった場合は、女との賭は無効とする』 「あ、あのガキ・・・用意周到に私の邪魔をしてくれるじゃないか」 「じゃあ、お願いしますね」 にこやかに頼んできた町人を邪険に突き飛ばした夜主に続いて、 梨乱も村を囲む城壁の階段を登っていった。 町の城壁に登って偵察すると、確かに巨人が近づいてきていた。 まだ例の丘よりは向こうにいるようではあったが、来襲は時間の問題だ。 「ああくそ! どうやったらあの土坊主を倒せるんだ!」 「夜主さん、冷静に冷静に・・・」 「夜主様、私が何とか致しましょう」 夜主は、疑惑に満ちた目を自らの指に填めた捜魂環へと向けた。 「言っちゃあなんだが、お前は当てにならん」 不信感丸出しの夜主の答えに涙する捜魂環を慌てて梨乱が慰める。 「まあまあ夜主さん。ねえ捜魂環、何か考えがあるんじゃないの?」 「はい。あの巨人はおそらく宝貝の力で形作られているのでしょう。 そして、私は前にもあの巨人に―そう、宝貝にも会っています。 ですから、宝貝の在処を探し出せるはずです」 「待て。あの巨人の中に宝貝が組み込まれているとは限るまい」 「あれだけの巨体を操っているんだから、少なくとも核となる物くらいはあると思う」 「・・・一理あるな。ならば、それで行くか!」 「ふう、ようやく気付いたのか。だが、倒されては困るのだよな。 何しろ、こいつは思い出の品だからのう」 いつの間にか、若者は村の中へ立ち戻っていた。 そして、先程まで夜主達がいた城壁の上に座って自らの宝貝を、 いや、その向こうにあるであろう過去を懐かしそうに眼差しを注いでいた。 梨乱たちが地上へ降りた時には、巨人は町まであと十間(約18m) の所まで辿り着いていた。巨人は大きいものの動きは遅いので、 そう近い場所ではない。時間はたっぷりとは言えなくとも十分あるはずだ。 「捜魂環、奴の核はどこにある!」 「暫くお待ち下さい。……巨人の額です」 夜主は素早く巨人の膝を足がかりとし、そこから一気に跳躍して腕に飛び乗った。 巨人の堅さが今回は夜主に幸いしていた。 「夜主様! 核が移動しました。核は喉に……いえ、左胸へ移りました!」 「何だと!?自力で移動出来るってのか? 梨乱、私は胸より上を担当する。お前はその下を頼む!」 「そんな事言っても私には武器もないのよ!」 焦る梨乱に、武器を持った村人達が駆け寄ってきた。 巨人の肌の強度と村人達の武器の強度を比べてみたが、 何とか一度くらいは耐えられるだろう。尤も、一度使ったらその武器は 打ち直さなくてはならないだろうが。それとも廃棄処分だろうか。 夜主たちは二人がかりで核を追った。しかし、核は巧みに移動して 梨乱たちから逃げ続ける。とはいえ逃げることで精一杯なのだろう、 巨人の歩みは止まっていた。否、少しずつ村へと近づいていた。 梨乱は攻撃を加える度に武器を交換しなければならない。 その隙に巨人は歩みを確実に進めているのだ。 いつまでも続きそうで、その実、今にでも終わりそうなイタチゴッコだった。 その内、巨人と防壁の距離は3.6mまで近づいてしまった。 力を振り絞って応戦する二人だが、巨人は防壁まで近づいた事で気分を良くしたのか、 移動の速度が上がっていた。二人が防壁の破壊を覚悟したその時。 「疾っ!」 もう聞き慣れたかけ声と共に飛来した烈風が、 二人を散々悩ませた核をいとも簡単に破壊した。 「またか? 自分一人だけ目立ちやがってあのガキ!」 そう、巨人の核を破壊したのはまた、あの若者であった。 「くそう、今度という今度は許さん……を、ををっ!?」 核が破壊された事により、巨人は一気に崩れ落ちた。 巨人の上にいた夜主は何とか無事着地した。俊地踏が着地の衝撃を吸収してくれる為、 夜主の足に衝撃はほとんど来ない。土煙の中から、 片手に見知らぬ男を抱えたあの若者が姿を現した。その手にある男は気絶していた。 町中の人々が見守る中で若者は片手を挙げ、 「宝貝使いはこの通り捕まえた。我々の勝利だ!」 と高らかに宣言した。その若者に夜主は詰め寄る。 「何、一人で格好を付けていやがる! それに宝貝使いを捕まえたならさっさと気絶させちまえばいいだろうが!」 「かっかっか。折角お主たちが額に汗水垂らして頑張っておると言うのに、 それを邪魔するなんてわしには出来なくてのう。 そうそう、賭はワシの勝ちのようだのう。 では、約束通りこの宝貝は諦めて貰おうか。かっかっか」 「ふざけるな、こんな約束なんか無効だ。ええい、こうなったら力ずくでも・・・」 「疾っ!」 若者は襲いかかってくる夜主を町の中へと遠く飛ばした。 その後、町人が我先にと町を救った英雄となった若者の周りへと集まってくる。 「その男が今回の首謀者ですか?」 「うむ。おい、起きろ」 活を入れられるとすぐ、男は懐を確かめた。だが、なかなか探し物が見つからない。 端から見ればそのような行動を取っていた。」 「お主が探しているのはこれかのう?」 若者が手にぶら下げていたのは、人形を操る道具によく似ていた。 しかし普通の道具と違って、糸の中には蜘蛛がぶら下がっているモノもあった。 「か、返せ!」 「ふむふむ。こうやって念を込めて、と・・・」 若者が目を閉じると、今まで蜘蛛がぶら下がっていなかった糸の端が変化して、 蜘蛛の形を成した。若者が目を開ける、と同時に蜘蛛が垂れ下がっている糸が切れた。 蜘蛛は地上に落下し、そこに小さな人型を作った。 ほうほう・・・。周りを取り巻く町人たちが、今まで自分たちを悩ませていた 巨人の正体に気付いた。これは小さな人型だが、大きな人型を作れば当然、 土巨人が出現する事になる。それに、道理で何度でも巨人は出てきたわけだ。 「おや、お前は李三じゃないか」 村人の一人が宝貝使いを見て、村の人間と看破した。 「そういえば、確かに李三だよな・・・この頃見ないと思ったら・・・」 「俺たちが李三を責めたのを逆恨みしたんじゃないか?」 「ふざけんなよ、こいつはいつも失敗ばかりしやがって・・・」 おたおたと慌てふためく李三に、村人達が拳を固めつつにじり寄って・・・。 * 「では、これはお主に渡しておこう」 若者は、梨乱に今まで町を騒がしていた原因となっていた宝貝を手渡した。 「いいんですか? 私がもらっても」 「別に構わぬよ。だが、これだけは渡せぬぞ。色々と愛着もあるからのう」 愛おしそうに、若者はいつも持っている棒状の宝貝を撫でた。 ついでに懐から清潔そうな布を出してきて、念入りな掃除を始める。 最後に一つだけ、梨乱は訊ねてみることにした。 「野暮な質問かもしれませんが、どうして、人間界に留まっているのですか?」 「ふむ。それはな、ここの方が色々と面白いことがあるからだよ」 そう言って若者が指差した先には、顔色を変えて迫ってくる夜主の姿があった。 『傀蛛糸』 対象を操るための操り糸の宝貝。その気になれば鉄でも真鋼でも操ることが出来る。 欠陥は、操る対象に埋め込まれる”蜘蛛”そのもの、そして使用者から蜘蛛まで 指令を繋げる仙術の流れに対しての隠蔽機能が装備されていないこと。 よって仙人はおろか、修行中の道士にさえも簡単に察知されてしまう。