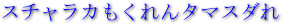
雪はふり続いていた。ややもすると4月まで雪が降っているこの地方では
決して珍しいことではない。
靴が雪にその足跡を記しても、残っているのはわずかの間だけ。
すぐに降り積もった雪に覆われ姿を隠してしまう。
それでも、祐一の足跡は一日は残っているのではと思わせた。
「急げあゆっ! 追いつかれたらどうなるか分かってるだろ!?」
祐一は走っていた。それも全速力でだ。学校のマラソン大会でも
これほどの速さで走ったことはない。口はばくばく、ぜーぜーと。
胸もどくどく波打ち体の限界を知らせている。それでも止まることはできなかった。
祐一の後方には女の子が一人。うぐぅうぐぅ喘ぎながらついて走っている。
少なくとも当人はそのつもりだった。まわりからはどう見えていようとも。
「どうして食い逃げなんかしたのぉっ!」
あゆは叫ぶ。祐一が食い逃げしたとき、同伴していたあゆも
成り行きで走り出していた。もしかしたらあそこで知らんぷりをしていれば
よかったのかもしれない、などとまで考える。
「決まってる! 金がなかったからだろ!」
たい焼きの袋をしっかり抱え込んだまま、祐一も叫んだ。
すると、声と一緒に気力まで外に飛び出してしまったように、
祐一の走り方は急に危うくなった。それはあるいは良かったことなのかもしれない。
その直後に祐一に体当たりをされた女の子にとっては。
「きゃっ」
体当たりされた女の子はかぼそい悲鳴をあげて崩れ落ちた。
女の子が持っていたビニール袋から雑多な日用品がこぼれる。
限界に近かった祐一の体は意志の鎖から外れて、
力無く倒れる。前向きに―少女の上にばったりと。
「はぁ、はぁ、はぁ……あれ、祐一くん?」
ゆっくりとした足取りで走っていたあゆも現場に辿り着く。
そこで展開されている光景を見て、あゆは不意にイヤな感じを受けた。
疲れた体をむち打って祐一の手を取り、二人の体を離す。
あゆに引っ張られて、女の子からずれ落ちた祐一の顔は雪に埋まった。
冷たさが祐一の脳を覚醒させた。顔を上げてぶつかってしまった女の子を見る。
大人しそうな顔つきの女の子だった。なんとなく守ってあげたくなるタイプ。
柄にもなく祐一は赤面して辺りの林に目を逸らす。
「こらあ〜〜〜っ! どこいったぼうず!」
エプロンをかけた青年の声が三人の耳を通り過ぎた。
祐一は必死に頭を回転させていい案を出そうとする。
なにか、なにかあるはずだ。大人しく謝ることから青年を迎え撃つことまで
いろいろと考えてゆく。
その時、祐一は自分の顔に注がれている女の子の視線を感じた。
何が起きているのか分からないから教えてほしいと頼むその瞳。
「あゆ、ここは俺に任せてくれ。俺がなんとかしてあいつをここで止めるから、
お前はこの袋を頼んだぞ」
そう言うと祐一はあゆにたい焼きの袋を渡した。
「え? え?」
祐一をここに残して自分だけ残る。後ろめたさ以上にイヤな感じが
あゆの頭を支配した。それも、さっきより強い感情で。
「早くいけーっ!」
戦友だけでも逃がそうと躍起になる傷病兵の気持ちになりきった祐一はそう叫んだ。
その叫びに押されてあゆも大事に袋をかかえて走りだした。
「あの……」
「しっ、黙って。あとで話してあげるから」
祐一は女の子に近づいて知り合いに見えるように振る舞った。
息を潜める怪しげな二人組。しかし青年は彼らを全く無視してあゆを追っていった。
それでも緊張を解いたりはしない。青年が視界から消えて初めて
祐一は緊張を解いた。
「うおっしゃ、パートナーを変えて目眩まし作戦成功だ!」
力を込めてガッツポーズをとる。
「あの子のことはいいの?」
「あゆなら、あとでおわびに何かおごれば忘れるだろう」
うんうん、と自分で納得する。横から目で質問してきた女の子に、
祐一はお金が無かったこと、それで仕方なく食い逃げしたことを話した。
「……祐一さんは悪い人?」
「何を言う。俺は根っからの善人で通ってるぞ」
もちろん真っ赤な嘘だった。それは女の子も分かったらしく、
くすくすと笑っていた。
辺りにはまだ女の子の荷物が散乱していた。
黙って祐一がそれを拾い始めると女の子も思いだした。
そして5分もすると、女の子のビニール袋は満杯になった。
女の子は落とし物を拾って手伝ったことを感謝した。
「ありがとう。お礼に……これをどうぞ」
少女が差し出して来たのはカップのアイスクリーム。
雪よりは黄色がかっているバニラアイス。
「え? 悪いって。もともと俺のせいで落としたわけだし」
「だったら出世払いで」
そこまで言われて断るつもりはなく、祐一は言った。
「……わかった。近いうちに払うからな」
けれども。祐一は思いに耽った。休みが済めばここにいなくなる自分の、
近いうちはいつなのだろうかと。
「はい、どうぞ」
女の子はカップとスプーンをセットにして祐一に渡してくれた。
よく考えてみれば、この寒い中アイスを食べるのか?
それでも祐一はカップのふたを開けた。まあ人のおごりだし、
との考えが浮かんだからだった。
スプーンはアイスクリームのケースの上に置かれている木のスプーンだった。
そういえば、これってどっちが持つほうなんだ?
中央でくびれたスプーン、その上下には形の違った楕円が描かれているが、
どちらも大きさは同じようなものだ。
祐一はスプーンをアイスに突き刺した。
「な、なんて堅さだよ。スプーンが通らないなんて……」
上下を入れ替えて試してみる。しかしお持ち帰り自由の木スプーンの
歯の立つ相手ではなかった。
女の子はどうなんだ? とちらっと見てみれば、スプーンを口にくわえて
幸せそうにしていた。くそう、どうやって口の中に入れたんだ?
祐一にも意地がある。それも人並み以上だ。無理にでも力を入れてみる。
ぼぎっ……ッ
迫力無いぱさっとした音を立ててスプーンは折れてしまった。
「どうしたの?」
顔色の悪い祐一に気づいて女の子は声をかけた。祐一は歯切れ悪い口調で答える。
「いや……スプーンがさ……」
アイスクリームを口に運びながら、女の子が折れたスプーンをまじまじと見つけた。
一口、二口……力を入れている様子もなく、女の子のアイスはその間も減っていた。
その指さばきは祐一にとって魔法を見ているかのようだった。
「おかしいね……ほら」
女の子はスプーンをアイスの表面に重ねた。次の瞬間にはスプーンの上に
アイスが乗っかっていた。
「どうぞ」
女の子は自分のスプーンですくったアイスを祐一の口に持っていった。
例えば今、横に座って自分に手を差し伸べているのが従妹の名雪やあゆだったなら
照れもなく食べられる自信のあった祐一だったが、
今日初めて会ったばかりの少女というのは……思い悩むうちにアイスはスプーンの上で
溶けてゆく。そしてついに自然の力に耐えられなくなって雪と同化しようと―
ぱくっ。すかさず祐一はスプーンごと口に含んで見事にキャッチした。
それからはっと気付く。気付いたら―動けない。
女の子は祐一がいつまでたってもスプーンを話さないのを見て、
くまさんポーチから木スプーンを新たに取り出した。
「それを俺にくれたらよかったのに……」
祐一は恨めしそうに新しいそれを睨んだ。
言葉に合わせてまだ口に含んでいるスプーンが上下に揺れる。
「え?……あっ」
ようやく女の子も自分のやったことに気付いて、頬を紅潮させる。
「え〜〜〜〜と……」
「はは……」
二人の間に気まずい雰囲気が立ちこめる。
あゆはまだ逃げていた。そう、明らかに体格が上のエプロン姿の青年に
まだ捕まっていなかったのだ。道をそれて林の中に入っていったからだ。
それはいいのだが、今あゆは迷ってしまっていた。
もともと知らない道をただ前を見て走っていた。
それを故意に道から外れていったら、方向が分かるはずもない。
もしかしたらこのまま自分は迷って出られないのではないか。
そんな恐怖から涙も止まらなくなっていた。それでもあゆは歩いた。
歩かなかったらどこにも出れないからだ。
そんな、涙ににじむあゆに見覚えのある後ろ頭が草に隠れているのが見えた。
あれは祐一君だっ! あゆは最後の力を振り絞って涙を振り切って走り出した。
「祐一くんっ! ヒドイよボクだけ置いてゆくなんてっ!」
憎まれ口を叩きながらも、あゆはひしっと祐一に抱きついた。
「おー、すまんすまん」
口先でしか謝っていないことは今のあゆには到底許せなかった。
ぽかぽかと祐一を殴りつける。
「う〜〜〜っ、怖かったよぅ。怖かったよぅ」
「……どうしたのか知らないが、ごめんな」
悲しみを受け止めてくれる相手が目の前にいる。
あゆは嬉しさのあまり、また涙が止まらなくなった。
「……そう、置いてけぼりはイヤ……」
女の子が俯いて呟いたその声は誰にも聞こえていなかった。
でも、聞こえていたとしても、その言葉の内に秘めた内なる想いに気付くことは
出来なかっただろう。みんな、まだまだ子供だった。
「う〜、もう食い逃げなんてしないもんっ!」
「何ぃ、食い逃げだと!? その年にして食い逃げとは末恐ろしい奴だな」
「うぐぅ……祐一君が最初に始めたんじゃない」
「そうだっけか? う〜ん、俺の記憶とは違うんだけどなあ……」
「あっ!」
突然の女の子の悲鳴にあゆと祐一は咄嗟に身構えて辺りに警戒した。
しかし、エプロン姿の人間なんて何処にもいない。
「アイスクリームが溶けちゃう……」
あゆと祐一の二人は勢いよく前に突っ伏した。
祐一の手元にあるアイスクリームはまだまだ十分に堅そうだった。
さすがに氷点下の気候はひと味もふた味も違う。
それでも、ようやくスプーンが入るくらいには溶けていた。
自分の手でアイスをすくって口に運ぶ。
とても冷たいはずのそれは、何故だろう、冷たさよりも温かい感じがした。
それは、栞自身も覚えていないようなかすかな記憶。
紡ぎだされた物語は、やがて―